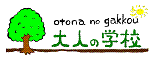 トップ > さいたま寺子屋サロンの記録 > 記録
トップ > さいたま寺子屋サロンの記録 > 記録テーマ:「目からウロコの音楽修業」
|
開催日:2010年3月20日(土) 話し手:谷口正さん(コーヒー屋シュッツ) |

目次
- お稽古ごとは楽しくなくては
- 音楽を何かになぞらえて理解する←情緒的理解ではわかりあえるか
- 音楽は暗記科目か→完全5度、長3度を目で覚えるだけで、耳で聴くことをしない
- ハーモニーを体感する
- 音楽で必要なものは、いらないものは
- 音楽を理解するとは
- 音楽は世界の共通の言葉?
- 言葉と音楽
- 高校の音楽授業はドイツ音楽とアメリカ音楽だけだった
- 教会音楽の面白さ
■お稽古ごとは楽しくなくては

昭和22年(1947年)、京都生まれです。昭和40年代(1965-74年)がちょうど青春時代でした。私の親は、自分がやりたかったことを子どもにやらせたいということで、5歳から私にバイオリンを習わせました。もともと人から強制されるのがいやな性格で、毎週1回のレッスンはいやでいやでたまりませんでした。
バイオリンを習ったときに、音楽って楽しいなと思わせてくれればよかったのですが、先生5人くらいにかわるがわる習いましたが、みな同じメソッドで鈴木方式の教則本でした。
そのメソッドの最初は、「キラキラ星変奏曲」の練習です。 譜例①キラキラ星のテーマ ドドソソララソ~♪このテーマを変奏するのですが、弓をきちんと同じ音を等分にひく練習や、8分音符や付点音符の変奏など、かなり機械的なんですね。技術の基礎の基礎なので、子どもは全然おもしろくないのです。いやになって行きたくなくなります。レッスンに行くと言って、よく加茂川で遊んでいました。
同じ「キラキラ星」のテーマでモーツァルトも変奏曲を作っています。
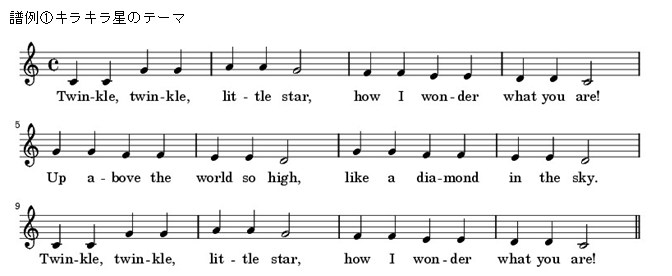
音楽①モーツアルトのキラキラ星変奏曲
機械的な変奏とは全然違いますね。いきなりモーツァルトの天才は真似できませんが、楽しさがあふれ出るような音楽でないと、やっぱりおもしろくないです。
それでもいやいや行っていましたが、発表会の時は門下生が集まって合奏する、この合奏は楽しかったです。フーガなんか好きでした。おっかけながら演奏する曲です。その時弾いた曲にバッハの協奏曲がありました。こんな曲です。
音楽②バッハの2つのバイオリンのための協奏曲
生き生きとしたスピード感がある、なんとスリルに満ちた音楽でしょう。バッハだけではなく、ビバルディなども好きでしたね。こんなふうにバイオリンや音楽の教師が伝えてくれれば良かったと思います。
中学生までそんなかんじでバイオリンをやっていました。3年生の時「受験が大変」とか親に騒いで、とうとうバイオリンをやめました。
■音楽を何かになぞらえて理解する←情緒的理解ではわかりあえるか
その頃、1960年前後の日曜の朝、NHKラジオで曲を30秒ほど聞かせて、どんな曲かという番組がありました。曲の一部を聞かせて物語風に話し、その後リスナーから募集した詩に曲を付けて即興で唱うのです。即興で唱うというのが面白くて、私はこの番組が好きで、毎週聴いておりました。
曲の一部を聴かせて物語るというのは、例えば「のだめカンタービレ」で有名になった次の曲なんかがかかります・・・
音楽③ベートーベンの交響曲7番第2楽章
これを聴いて「夜が明けきる前、お葬式の行進が始まりました。暗く、重々しく歩いていきます。やっと夜が明けてきました。お日様が出てきて少しやわらいできて、ほっとしました」などと物語るわけです。そうすると、審査員が「すばらしい情景ですね。でもお葬式の行進より、王様の行進の方が僕は合っていると思うなあ」とか、さらに勝手なことをいうわけです。
こんな番組を聴くことで「音楽とは」ということについて、だんだんイメージが形作られていきました。つまり音楽を理解するとは、音楽を物語などになぞらえることなのだという理解です。このようないわば情緒的理解でわかりあえると思っていました。しかしこの曲の例でもわかるように、ある人はお葬式の行進と理解し、ある人は王様の行進と理解しているのですから、すれ違って理解しているわけです。
■音楽は暗記科目か→完全5度、長3度を目で覚えるだけで、
耳で聴くことをしない
1960年の安保の年に中学に入学したのですが、この頃の音楽の授業は目で見て覚えることが中心でした。音程というのは、1度とか2度、オクターブはドからドが8度。試験にも出る完全5度、長3度、短3度・・・などを、目で見て鉛筆で五線譜の間がいくつあるか数えて、半音がいくつあるかを数えて、とやってませんでしたか?
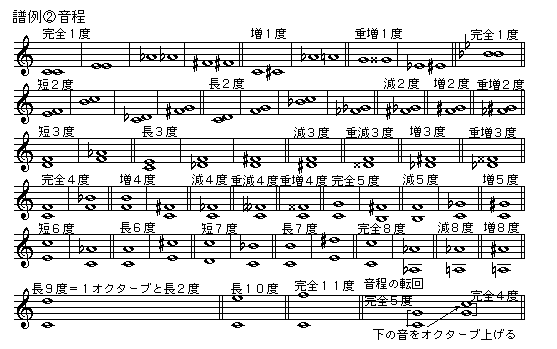
じゃあ完全5度や8度ってどういう響き? ちゃんとこたえられない。完全五度、8度とは、映画「2001年宇宙の旅」のテーマ曲の「ツァラツストラはかく語りき」の冒頭にトランペットが奏する音階ですね。
完全5度を目で見て覚えさせるけれど、響きでは教えてくれない、そういう授業を受ける生徒には、音楽は暗記物という意識がありました。そういう教育を受けながら高校に入りました。
■ハーモニーを体感する
入学式のあと、陸上部に誘われましたが、先輩が合唱団にいてそちらに引っぱられました。私の高校では、男声合唱、女声合唱、混声合唱がありました。顧問の音楽教師はいましたが、指揮者も生徒がやって、自分たちが好きな曲を歌っていました。まあ、それも善し悪しがありますけれど、その雰囲気は好きでしたね。僕は男声合唱と混声合唱に入っていました。男声合唱というのは、へたでもハモっているように聴こえる。合っているように聴こえる。唱っていると、その雰囲気にさらにしびれる。そのしびれる男声合唱を1曲お聴かせします。
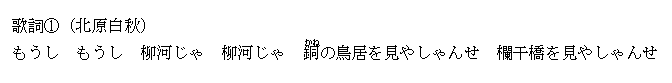
音楽④多田武彦の男声合唱曲「柳河風俗詩」
"みやしゃんせ みやしゃんせ"というところが、なんとも深々とした、憧れ一杯の懐かしさがあるでしょう。しみじみとするでしょう。男声合唱のハーモニーの醍醐味の一つがここにあります。この曲を作曲した多田武彦さんは、1950年代に銀行員をやりながらの日曜作曲家だったのですが、日本の男声合唱団はほとんど多田さんの曲を歌っています。多田さんは草野心平や北原白秋の詩に、日本人の心情にぴったりとした(演歌に似たある意味ではセンチメンタルな)メロディー、リズム、ハーモニーを付けました。それで特に感激屋の男どもには好きな人が多かったようです。
次に女声合唱を聴いてみましょう。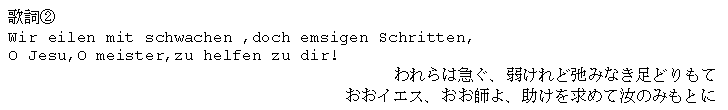
音楽⑤バッハのカンタータ78番より女声デュエット
コントラバスとチェロとオルガンの通奏低音が女声を支えるとともに、歌詞の「急いで、急いで(eilen)」に呼応したうれしさ溢れるリズムを軽やかに奏でています。女声はこの通奏低音の上に乗っかるだけで良いのです。それは、フイギャースケートのペアのように、男性が女性を持ち上げるときのようです。よいしょとは持ち上げないで空気のように持ち上げるといいます。歌も女性はふわっと乗っかる。これが実は大変な努力のたまものなんです。声だけ聞くと可憐ですが、ふた回りもあるようなすごいおばさんが歌っていたりします。
ドイツでは、大男はプロレスラーかオペラ歌手かになりなさい、と言われるそうです。しっかりした体がないと、高い音程でもどならないで軽くふわっと出せません。からだがバネのようになっていて、のどや胸郭を十分開いて声を出さないと、このCDのような声は出せません。
ピアノ伴奏でのリサイタルと、オーケストラ伴奏でのリサイタルか、どちらがたいへんかというとピアノのほうが大変です。オーケストラは何十人もバックにいるからそこにちょいと乗っかればいいのです。ちゃんとした歌手は声を乗っけるだけです。駄目な歌手はオーケストラに負けじと力みますが、力み声はかえって後ろまで届きません。
なぜ女声合唱は可憐、軽やかな響きで、男声は分厚く豊かな響きになるのでしょうか。男声の方が声が低いから?そうですね。でもなぜ低いと豊かに聞こえるのでしょう。倍音という現象が大いに関係しています。男声合唱の方が豊かな響きに聞こえ、ハーモニーしやすく聞こえるのは、男声合唱の方が倍音が豊かだからです。
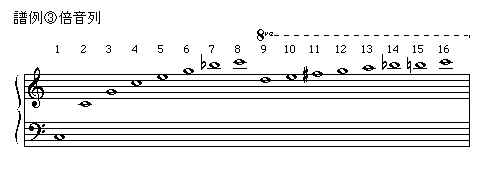
倍音というのは、例えばピアノで最も低い方のドと弾くと、人間の耳には聞こえにくいですが、一緒にその2倍、3倍、4倍、・・・・の周波数をもつ音が響いています。男声は元の音が低いので倍音も沢山響きます。女声は高いので、男声と比べると倍音が少なくなります。従って、男声は豊かな響きに聞こえ、女声は軽やかな響きに聞こえるのです。
さっきの映画「2001年宇宙の旅」のテーマ曲では、ド、ソ、ドという倍音列そのままの音階を冒頭で聴かせ、倍音が限りなく上方に続くことに引っかけて、限りない宇宙の果てをイメージさせたかったのではないでしょうか。
蛇足ですが、私が聞いた範囲の日本の合唱団で、8度や5度がいつもちゃんと合っている合唱団は数えるほどしかありません。同じ音が微妙に合わないのですから駄目なんですが、それを認識できていない。「耳が悪い」というか、倍音が聞こえてないのですね。実は私もそうなのですが。
さらに蛇足ですが、世界で有名な少年合唱団、例えばウィーン少年合唱団の入団試験で、一番重視されるのは耳の良さです。次が頭の良さ、3番目にやっと声の良さが来ます。耳がよければ少々声が貧弱でも、ソリストでない限り合唱したときにちゃんと倍音が響かせられればダイナミクスは十分ですし、倍音を響かせるために大勢の中で自分はどうしたらよいかを瞬時に判断できる頭の良さが求められるわけです。
■音楽で必要なものは、いらないものは
音楽の先生は、生徒のクラブ活動に顔や口を出しませんでしたが、音楽の授業はこれまでの音楽観を根底から覆す厳しいものでした。
最初の授業で、レコードを聴かせているときでした。生徒は私語が多く、ながら聴きで聴いているわけです。そうすると突然どえらい大声で「いましゃべっている奴は出ていけー!」と、先生がものすごく怒るのです。出ていくまで怒るのです。生徒はあっけにとられて、さすがにシーンとしてしまいます。
出ていかせてから、「君達、音楽にとって必要なのは何ですか」と聞くんです。急にそんなこと聞かれても、誰も返事ができないのです。そうすると「音楽で大事なのは音。音が一番大事。でも一番必要ないのも音です」と先生が言うのです。「なんや、あたりまえやん」と生徒は思うのですが、先生はそれを見透かしたように、「君ら、そんなこと当たり前、と思うやろ。そやけどさっき音楽聞かしたとき、しゃべってたやろ。君らの声は、音を邪魔する、必要ない音や。そやろ。それがわからん奴は出ていけ。」と言いました。
今まで音楽の授業というのは、目で見て覚えることが中心でしたから、この出来事で、それとは全然違う授業なんだなということが、はっきり印象づけられました。音楽についての既成概念の一つが打ちやぶられました。
余談ですが、ジョン・ケージという作曲家の「4分33秒」を知っていますか?
音楽⑥:J.ケージの「4分33秒」
ピアニストがステージに出てきて、ピアノ前に座り、ふたを開け、4分33秒ピアノは弾かないで座っているだけなんです。ピアニストへの指示は、第1楽章から第3楽章まで「休止」とされています。
30秒位すると聴衆がザワザワし始めます。ホールの音や外の音も聞こえたりします。いろんな音が聞こえてきます。J.ケージはそのような"騒音"を聞かせたかったようです。ケージの(休止のままでなにも演奏しない)「4分33秒」でさえやはり音は聞こえていたわけです。
ケージのこの作品は、友人である画家の個展に触発されて作ったと言うことです。その個展では、キャンバスが真っ白な額が数枚並んでいるだけの部屋があって、天井とか壁に照明が取り付けてあってキャンバスに人の影が映ったりする。画家はそれをみてほしかった、というのです。
■音楽を理解するとは
授業では、音楽で一番大事なのは音、ということをさらに強固に印象づけ、これまでの音楽に対する既成概念を一掃する第2ステップが次に待っていました。たとえば次のような曲を聴かせます。
音楽⑦ハイドンの弦楽四重奏曲「皇帝」第2楽章
これは最近テレビで聞いたことがある音楽でしょう。ドイツ国歌です。オリンピックで流れていましたね。どういう曲ですか?ロマンティックな曲です、と言ったら、バカヤローと言われました。ひとりひとりの「ロマンティック」はちがう。その言葉では説明したことにはならない。ではどう答えるか。先生が言うには、どういう音楽?と聞かれた時には、こういう音楽です、ともう一回弾くのが一番いい。次にいいのはピアノで弾く、ピアノの弾けない人は楽譜に書く、楽譜が書けなかったらメロディーの一節でも歌う、オンチで歌えないひとは、「バイオリン2本とビオラとチェロの曲」、と答える。徹底的に音にこだわった理解の仕方ですね。
これは音楽についての一つの考え方ですね。即物主義に近い。オーケストラの練習風景を聞いたりすると、指揮者は自分が思っている音楽を自分で唱って団員に伝えようとします。「タッタラ、タッタラ、ター」とかやります。言葉で伝えようとする指揮者もいますが、最終的にそれでも満足な音楽にならない場合、徹底して唱います。口三味線、口移しというぐらい。
■音楽は世界の共通の言葉?
音楽は世界共通の言葉だと言われます。ド、ミ、ソで作られた音楽がグローバル化しているので、日本で作られた曲も、ヨーロッパやアジアで作られた曲も大差ないように聞こえます。
しかしドイツの音楽とフランスの音楽は全然違う。先程の「ツァラツストラはかく語りき」を作曲したリヒャルト・シュトラウスは、ドビュッシーのオペラ「ペレアスとメリザンド」を観て、「この音楽には脈絡がない、ばらばらだ、楽句がない、展開がない」とボロクソに評したそうです。音楽の区切りと抑揚の付け方がドイツとフランスでは全く違うので、シュトラウスはほとんど生理的に、ドビュッシーの音楽を受け入れることができませんでした。
私たち日本人も、有名ドイツ人歌手がアンコールにサービスのつもりで、「ゆうやー、けこやけー、のあかと、んぼー」とか唱うのを聴いたりしたら、それまでの「冬の旅」の感動も興ざめしてしまうわけです。
■言葉と音楽
同じ曲でも、訳詩で歌ったら全然違う音楽になりかねません。ベートーベンの第9の合唱の部分を聞いてみましょう。
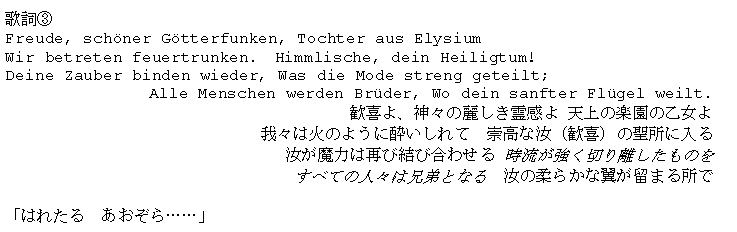
音楽⑧ベートーベンの交響曲9番第4楽章
ここでは「Freude,schöner」と「eu」と「ö」にアクセントが置かれますから、2拍子に聞こえます。しかし日本語訳詞では「ハレタルアオゾラ」と唱いますが、日本語にはアクセントはありませんから、1拍子の音楽になってしまいます。これは音楽としてはドイツ人には全く通じません。シュトラウスと同じように「何じゃこれは」と思われます。これはたとえドイツ語歌詞を見て「フロイデ、シェーナー」とカタカナ読みで唱っても同じことです。
■高校の音楽授業はドイツ音楽とアメリカ音楽だけだった
高校の音楽の先生はフランス音楽を聞かせませんでした。「僕はフランス語ができませんから」と言っておられましたが、徹底していましたね。そこまで考えられた音楽の授業が今の学校であるのでしょうか。
私は合唱をやっていたので、言葉と音楽の関係に特別興味がありました。大学では最初グリークラブに入りました。それなりに有名な学生男声合唱団で、団員も都会的でスマートな人が多かったのですが、そういう伝統あるクラブなのか、先輩が理由もなく偉そうにしていたので、それがいやで夏にはやめて、学生聖歌隊という所に入りました。私はクリスチャンでもなかったのですが、そこでは先輩がえらぶらず、自由な感じで、そこで先程のバッハのデュエットも初めて知りました。バッハが私に教会音楽への門を開いてくれました。
■教会音楽の面白さ
教会音楽というのは聖書の言葉に曲を付けた音楽です。ハイドンやモーツアルトが出てくるまでの、西洋音楽の大きな柱の一つは教会音楽でした。 教会音楽で何が楽しい、面白いかと言えば、聖書の同じ言葉に様々な作曲家が音楽を付けているところです。
ここでバッハとシュッツの「マタイ受難曲」から同じ歌詞の曲を聴いてみます。ハインリッヒ・シュッツは1585年生まれで、バッハはちょうどその100年後の1685年生まれです。シュッツはドイツ30年戦争(1618-48)の時代を過ごしたひとで、様々な制約の中でドイツ語での教会音楽を究めました。シュッツを「ドイツ音楽の父」と呼ぶ所以です。因みに当コーヒー屋の名前はこのシュッツから来ています。
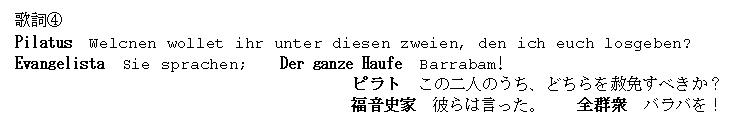
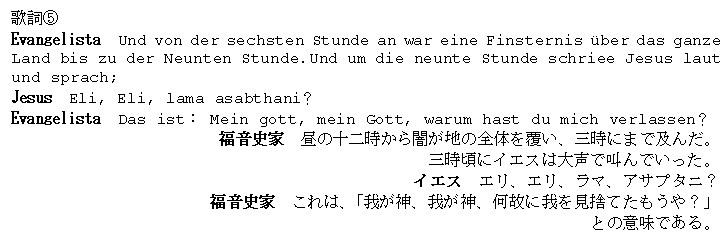
音楽⑨⑩⑪⑫バッハとシュッツのマタイ受難曲
「バラバを」と群衆が叫ぶところは、バッハはたった1回で表現しています。しかしその和音は減7度の和音が使われており、何とも言えないギリギリした不条理さが感じられます。対してシュッツは各パートに「バラバを」とフーガの形で数回叫ばせたのち、最後に4パートが合わさって「バラバを」とだめ押しのように言わせています。
次はイエスが息を引き取る場面ですが、バッハは「Eli,Eli.lama」の部分を下降音程で表現し、シュッツは逆に上昇音程で唱わせています。
なぜ同じ歌詞なのに違う音楽になっているのか。バッハとシュッツの聖書、情景等の解釈のちがいや、表現の型に1世紀の開きがあるからなのでしょうね。これを研究すると立派な論文が書けるくらいの興味深いことなんですが、まあそれは専門家にお任せして、私はもっといろいろ唱ったり、聴いたりを楽しむことにします。
以上
<スタッフ>テープ起こし:山野井美代
HTML製作: 〃
写真撮影 :山中昌江
|
お問い合わせ: NPO「大人の学校」 住 所: さいたま市南区別所5-1-11 TEL/FAX: 048-866-9466 Eメール: otonano-gakkou@cure.ocn.ne.jp |
[制作] NPO(特定非営利活動法人) 大人の学校