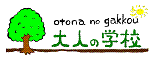 トップ > さいたま寺子屋サロンの記録 > 記録
トップ > さいたま寺子屋サロンの記録 > 記録著者の一人として
絵本「さっちゃんのまほうのて」(*)
を語る
(*) 発行1985.10.偕成社
|
開催日:2010年5月15日(土) 会 場:コーヒー屋シュッツ 話し手:野辺明子さん (先天性四肢障害児父母の会。さいたま市在住) |

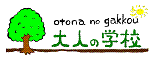 トップ > さいたま寺子屋サロンの記録 > 記録
トップ > さいたま寺子屋サロンの記録 > 記録|
開催日:2010年5月15日(土) 会 場:コーヒー屋シュッツ 話し手:野辺明子さん (先天性四肢障害児父母の会。さいたま市在住) |


今日は私の出産体験、父母の会設立のきっかけとなった新聞への投稿などにもふれながら、絵本『さっちゃんのまほうのて』についてお話しようと思います。
突然のへきれきのように、とても厳しい現実に直面したというのが、1972年、娘の出産でした。わたしにとって、最初の子どもでした。ちょっと仕事にいきづまってくたびれてしまい仕事をやめ、少しゆっくりしたいなと思っている矢先に妊娠に気がついて、もう仕事はしていませんでしたから、わりとゆったりと妊娠期間を過ごしていました。元気な赤ちゃんを産みたいと思っていましたから、食べ物にも気をつけていました。
女性でしたらきっと、妊娠中に一度や二度は、もしかして、自分のおなかの中で今育ちつつある赤ちゃんがもしも障害児だったらと考えたことがあるのではないでしょうか。でもわたしにかぎってそんな障害児を産むはずがないと、すぐそれを打ち消すように自問自答しながら、出産の日を迎えました。そして分娩室で「おぎゃー」という産声をきいたときに、産婦人科の医師に分娩台から、「先生、赤ちゃん大丈夫ですか?」って、聞きました。先生は、右手の指にほとんど指らしい指がなく、まるまって生まれてきたものですから、すぐ気がついたと思うんですけれども、言葉短めに「はい」とこたえてくださったので、すっかりわたしは安心して「あー、よかった。とりあえず、五体満足な子が生まれた」と思って、自分の病室に戻りました。
ところがなかなか赤ちゃんが自分のそばにつれてこられない。夜になっても、顔をみることもできない。おかしいなと思ったんですけども、はじめての出産だったものですから、「ミルクを吸う力が弱いから新生児室でお預かりしています」という看護婦さんの説明にあまり不安に思うこともなく、翌日をむかえ、2日目、3日目・・・。夫がなんとなく変だ、ということにもあまり気付かずに、3日目の夜、医師から初めて「実は野辺さん、赤ちゃんの指が・・・」って聞かされました。夫や双方の家族たちももちろん、出産当日に医師から聞かされてみんな承知していたけれども、今でもそういうことまだあるんですが、母親には赤ちゃんに何か問題があったことをすぐには言わない。ましてや38年前ですから一切伏せられていたんです。
はじめて医師から聞いたときに、どういうふうにその現実を受けとめていいのか分かりませんでした。「どうして?なんでわたしの子が障害児なの?」といろいろなことが頭の中を駆け巡って。無事に望みどおりの女の子が生まれたのに喜びや嬉しさがどこかに吹っ飛んでしまうほどのショックを受けました。将来への希望が急激にしぼんでいくような。夫は娘の将来への不安と、ショックを受けて動揺激しい妻をどう支えていくか、など大変だったと思います。ともかくわたしは娘とともに暮らすようになってからも、なかなか自分の子どもが右手の指を持たずに生まれてきた、障害を持って生まれてきたという現実が受け入れられませんでした。そのことを娘に本当に申し訳なく思いますね、今は。

夫とも「隠さないで育てなきゃね。明るい元気な子に育てよう」って、話はするものの、それができないのです。1月生まれですから寒いさなかは外へ散歩に連れだすにしてもいっぱい着せちゃいますと、よくわかりませんから気が楽なんですね。5月6月、最初の夏を迎えるころには、娘も6カ月を過ぎるとこう、手足を動かしますし、抱っこしてたってみえちゃう。わたしやっぱり近所の人に言えないんですね。自分の子どもは生まれつき右手の指が5本ない障害児だったと。で、外出時はいつも手袋で隠していました。
産院を退院する時に医師が、あまりにも衝撃をうけて涙、涙のわたしをはげますつもりだったと思うんですけれども、「野辺さん、今は医学が進歩しているから、手術をすればなんとかなりますから」って、話してくださった。わたしはそれに望みをかけました。手術すれば治るかもしれない、普通の手のように治せるかもしれないって。形成外科を受診しました。1歳の誕生日を迎えて体力が少しついてから手術をしましょうということで、1年先の予約をしました。1歳になったら手術をうけて、左手のように見た目よく治してやることにかけたというか。障害を治すことに娘の人生の幸、不幸がかかっている、くらいに思い込こんいましたね。手術がすんだら近所の人にもそれなりに言おうと思っていたんです。
でもあとで冷静になって考えれば、ない指をつくることはできないんですね。唯一あった親指の機能を最大限生かして、物をつかむ機能をいかす手術を1歳4カ月で受けましたが、5本指の手には治りませんでした。
生まれつき指がないという障害を治すことはできない。それがはっきりとわかるのに1年半かかりました。手術後の手を見た時に、「娘はこの手で一生生きていくのだ。自分のこの手を好きになるよう、隠さず、堂々と手を出していこう。指がないことがかわいそうなのではなく、親がそのことを隠す方がかわいそうなことだ」と思い至るようになりました。それから外出時の手袋を捨てました。近所の人にも生まれつき指が少なかったこと、手術でカニのはさみのような形になったことを話しました。
最初はもうひたすら隠して隠して育てていた。それはやっぱりわたしの心の中に障害児というものへのマイナスイメージしかなかったからだろうと。普通の子とは違う、普通の子より劣っている、それから、わたしが障害児の母親だという目で見られるのが辛い、などなど。障害をもつ人への偏見が自分の中に厳然としてあった、ということはショックでしたね。
そして納得できないから原因が知りたいわけですよ。でもほとんどが原因不明です。先天異常は人類がこういう姿かたちに進化してくる過程でのアクシデントであり、どんなに地球の環境が100パーセントクリーンであっても、先天異常は必ず何パーセントかの確率で起こる。突然変異も起こる。遺伝病を「その家に流れる血の汚れ」的なものとして忌み嫌うというか、恐れていましたが、遺伝病も、遺伝子に傷がつけば起こる。そういうことを今では理解できるようになりましたけども、当時は、なぜ?どうして?なぜわたしが?と、あってはならないことが起きた、という気持ちの方が強かったものですから、なかなかありのままに受け入れるなんてことはできなかった。
でもそういう日々の中で、娘が日ごとに大きくなっておしゃべりが上手になって近所の友だちとも遊んで元気になると、だんだんわたしの最初のショックも和らいで、子育てが楽しめるようになったんですね。3歳の誕生日を迎えた時に、その思いを新聞に投書しました。1975年2月、毎日新聞の『女の気持ち』欄です。わたしの娘の問題はわたしの家の、家族だけの問題なんだろうかって思う気持ちがだんだん広がっていったんですね。
娘が生まれた72年当時は、皆さんも聞いたことがあると思いますけど、サリドマイド薬害事件が社会的な問題になっていました。妊娠初期にサリドマイド剤の入った乗り物酔い止めや睡眠薬などを服用したお母さんから手足がないとか指がないといった外表奇形の子どもたちが世界中で生まれ、日本でもサリドマイド裁判が終盤を迎えていました。ですからサリドマイド薬害被害児としての、指がない、両手が肩からない子どもたちがテレビなどメディアでも紹介されていましたから、一般社会の人たちもそれへの理解はある程度もってしていたんですね。
でもそれは薬が原因で、当時の厚生省と製薬企業が損害賠償責任をとることに決まった、そういう子どもたちと、わたしの子どものように原因がわからないままなぜか生まれつき指がない、手がないという子どもたちの問題はやっぱり一緒じゃないんですね。
「奇形児」という言葉が生きている社会でしたから、やはりいろいろいやな思いをするのですね。だんだんとそういう現実への納得のいかなさ、怒りのようなものが私の中に芽生えていきました。もしかしたらわたしのように、そういう子どもを世間の目を気にしながら育てている人もいるんじゃないかと思うと、そういう人と出会いたい気持ちがだんだんと募ってきたんです。仲間がほしい、と。そんな思いで投書を思いついて。もしこれが採用されて活字になったら、読んだ人から、うちにもそういう子どもがいますよって連絡が入るんじゃないかという、そんな気持ちも確かにありました。
案の定、投稿が記事になったその日のうちに新聞社を通して何人かのお母さんから連絡が入って、電話口でお互いに話すだけでも涙涙で今まで積もり積もっていたものをワッとはきだすように喋りました。そのような電話がその後何日も続いたんですね。そして半年後の8月には「先天性四肢障害児父母の会」を作りました。
みんなと会いたい、これからのことを話し合いたいという、積もる想いをみんな抱えていたもんですから、パタパタパタッと親の会をつくるようになってしまいました。全国組織の親の会としてかなり精力的に活動を展開していきましたが、10年目に出版したのが『さっちゃんのまほうのて』です。
わたしたちは手足に障害をもつ子どもを育てる中でいろんなことを経験しますが、基本的には健常の子どもを育てるのとそんなに変わることはありません。ただ"みんなとは手足の形が違う"っていうことに子どもが気がついたときに、どう子どもに説明するか、は最初の大きな山でしょうね。ぱっと一目見て、あっ手がない、指がない、足がないっていうふうに、目にみえる障害の場合には、他人の視線とかいろんなことを子どもたちは体験しますが、そのことを本人がどう認識するかはいろいろです。わたしの家の場合も子どもがいつ気がつくか、気がついたら、生まれつきなんだってことはちゃんと話そうと夫とも話していたんですね。
あるとき台所で、ご飯の支度をしているときにトコトコトコってきて、「お母さん、お母さん、まいちゃんの手へん」って言って両手を広げました。わたしの両手をみつめ、ママはこっちもこっちも同じ、と。夫の両親とも同居していましたから、おじいちゃん、おばあちゃん、パパの手みんなの両手を見比べてもみんな右手と左手が同じなのに、自分だけ違うっていうその違いに、気がついたんですね。その時は"お母さんのお腹の中でけがをした"というような説明をしました。わたしその時に「いやだ、いやだ、こんなていやだ!おててがほしい!」って泣かれるかと覚悟していたんです。
でも幸いなことに娘は2歳7カ月ぐらいだったと思うんですが、それまで手のことでいじめられたことが一度もないんです。近所の遊び友達が5〜6人いてみんな娘と同じような年頃だったんですが、手術が終わって蟹のはさみのような手をした娘を子どもたちの中にほっぽり出して、お母さんがたがそれをちょっと遠く離れたところから見守ってくれているっていう日々の中で、近所の子どもたちは見慣れちゃったんでしょうか。"まいちゃんの手はこういう手"と。ずーっとこういう手だったから特に不思議にも思わなかったのかどうか。近所でいじめられたことがないから、娘にとっては、"こっちとこっちと形が違う""家族ともお友だちとも違う"手だけど、辛さとか悲しみにはつながっていなかった、ということだったのかなあと。他との、あるいは絶対多数との違いを責め立てられることがなければ、違いは違いのままでどうってことないんですよね。
ところが4歳で幼稚園入ったんですね。幼稚園に入園して、1か月も経たないころ、涙ぐんで帰ってくるような日が続きました。年長さんや年中さんが娘の右手に気がついて、娘をグルっと取り囲んで"変な手!"とか、"お前の手、気持ちわるい!"っていうわけです。怖いし、悲しくなりますよね。そして自分の手がみんなとは違うことを意識するし、それが悲しみにつながる経験もするようになるのです。自分では自分の手を何とも思っていないのに。
小三男の子の文章の中にこんな言葉があります。「もしその手どうしたの?とやさしく聞かれたら、うん、あのね、お母さんのお腹の中にいたときにけがをしたんだって、やさしく言ってやります」。これは作文の一節なんですけれども、わたしこの作文がとっても素敵だなって思ったのは、周りの子が、その手どうしたの?ってやさしく聞いてるんですね。周りの子にとっては指のない手が不思議でしょうがないわけですよ、で、率直に聞く。その聞き方が、気持ち悪い!お化けの手みたい〜っていうような、蔑むような聞き方ではなく、どうしたのその手?って本当に心から知りたくてやさしく聞いている、聞かれた子どもにもわかるんですね。この子はいじめたくて僕の手のことを聞いているんじゃない、と。そうすると、うん、あのね、と自分の手のことを素直に話せる。前よりもっと仲良しになれる。コミュニケーションが生まれる。この作文の子ども同士のやり取りの中に、わたしは障害を持つ人を理解する一つの鍵がある気がするんですね。不思議に思ったことはどんどん聞いていいんです、どうしたの?って。車いすに乗ってる人を見て子どもがあの人なんで車いす乗ってるの?って疑問に思ったら、車いすの人に率直に聞いていいんです。大事なのはその聞き方なんですよね。
こうした父母の会の子どもたちの日常から『さっちゃんのまほうのて』は生まれました。1985年に刊行されてから、今年の秋で25年になります。おかげさまで65万部ほどになりました。指のない女の子を主人公にした絵本がこんなに売れるとは、当初出版社も思いはしなかったと思います。幼稚園や保育園で読み聞かせに使っていただいたり、小学校で福祉の授業にとりあげていただいたり、一般の方々が心をこめて読んでくださったり、いろんなことから静かなロングセラー絵本になっています。
ご自身も左手の指がないしざわさよこさんがご自分の子どもたちやその友だちに障害について理解してもらおう、と絵本創りの企画をたてて、父母の会にも声をかけて下さったことから共同制作での絵本創りが始まりました。1979年のことです。
しざわさんは亡くなられた灰谷健次郎さんの『太陽の子』を連載していた月刊誌の編集担当者で、挿絵を描いていたのがたばたせいいちさん。たばたさんは、『おしいれのぼうけん』などの子どもの本でとても人気のある画家で、そのいきいきとした子どもの描写とお人柄の魅力から、絵は絶対にたばたさん、としざわさんは決めた上で障害児の児童書を数多く出している偕成社に企画を持ち込んだそうです。
原稿も何にもない状態でしたが、偕成社の当時の社長さんが、「わかりました、出しましょう。そのかわりいい本を作ってください」ってゴーサインをだしてくださって、それからしざわさんとわたしとで、絵本のテキスト原稿を書くことになりました。自分たちが絵本にしたいと思うエピソードをそれぞれが原稿に書き、持ち寄って、たばたさんと編集者としざわさんとわたしと4人で、月に1回か2回ぐらい集まって編集会議、というか話合いを重ねていきました。そうしてやっとテキスト原稿ができたのが3年後です。その原稿をもとに絵本作家のたばたさんが文章や全体の構成を組みたて、絵を描き、絵本として完成させてくださったわけです。完成まで足掛け6年かかりました。
わたしは絵本創りなんて経験したことありませんでしたから、テキスト原稿ができたら後は画家の手にゆだねる、原稿の文章ができるまで画家はノータッチなのかなあと。ところがたばたさんはそうじゃなくて、3年間ほとんど毎回、編集会議に出て一緒にストーリー創りに参加してくださったのです。指のない子どもたちやその親たちのことを深く知ろう、理解しなければさっちゃんの絵は描けない、と父母の会のスキーキャンプや運動会などいろいろな行事に参加してくださいました。スキーキャンプでは、昼間は子どもたちのスキー指導、夜は親や若いボランティアたちとお酒を飲み交わしながらお喋りの仲間入りをしてくれました。そこで出産当時の親の話を聞いたり子どもたちと遊んだりしながら、さっちゃんのイメージを膨らませてくださったようです。
皆で話し合ってさっちゃんの家にはもうすぐ赤ちゃんが生まれる、さっちゃんもお姉さんになる、という家族構成にしました。わたしの場合は娘は一人っ子なんですね。出産直後のいろんなショックも和らいで、もう一人子どもがほしいなと思う気持ちがあるにも関わらず、私は"もしまた障害児だったらどうしよう"などと考えてなんとなく次の子については躊躇する時期が続きました。障害のことをふっきれていなかったのですね。次の子が指はあってもダウン症の子だったらどうしようとか知恵おくれの子だったらどうしようとかあれこれ考えちゃう。どこかに"障害児は産みたくない"っていう気持ちがあったんでしょうね。なんとなく、一歩踏み出せないまま数年が経ち、結果的に一人っ子で終わっちゃったんです。
幼稚園のお友だちのおうちに赤ちゃんが何人も生まれた頃、「まいちゃんちはいつ生まれるの?お母さん早く赤ちゃん産んで」って子どもは無邪気に言ってきます。わたしははっきり答えられなくて「うん、そのうちね」と誤魔化す。そういう親の迷いを娘はちゃんと感じ取るんですね。
「ママ、わたしも大きくなったら小さな手の赤ちゃんを産むの?ママ、まいちゃんが大きくなって赤ちゃんを産むとやっぱりまいちゃんの赤ちゃんにも指はないの?」これは4歳か5歳の時の言葉です。遺伝の問題ですよね。遺伝なんて概念は、4・5歳の子どもにはないのに、やっぱり、お友達に指なし〜とかお化けの手っていじわるされたりしたときの辛さが、こういう言葉になったのかなって、わからないですが。自分に弟や妹がいないってことで娘はさびしい思いをしたと思いますね。
絵本では、お母さんもお父さんもいろんな悩み、迷い、戸惑いをそれなりに受け止めて、赤ちゃんを産むことを決意した家族にしました。障害があってもいいじゃないか、という肯定の気持ちを表したかった。「父母の会」の会員には下に弟妹を産んだ親はいっぱいいます。むしろそのほうが多いです。一人っ子の方が少ないかもしれません。"最初はショックでさんざん泣いたから次はもう障害児が生まれたって大丈夫よ"って人などまあいろいろですね。それぞれが家族のドラマを抱えているわけです。
でもやっぱりね、子どもは親を試すんです。まあちゃんという男の子とお母さんの会話をご紹介します。彼ももう35・6歳になりました。お母さんが不妊症で結婚8年目くらいにやっと生まれた子どもだったけど、両手合わせて指が2本しかないんです。それでも自動車を乗り回し、自動車販売の営業マンやってますけども。お母さんとおしゃべりしていた時に聞いた話です。「あの子が1年生のころかな、あの子も赤ん坊がほしくてたまんないのよね。でも、あるときね、『おかあさん、もし、生まれてくる赤ちゃんも、まあちゃんみたいにおててがなかったら、おかあさん、どうする?』って聞くの。わたしが『ああいいよ』って答えたら、とってもうれしそうに安心した顔してたわ」と。まあちゃんは無邪気に聞いてるけど親を試してるんですね。もし次の子も指がなかったらおかあさんどうするか。明るいその太っ腹のお母さんが、"ああいいよ、手がない赤ちゃんでもお母さんうれしいよ"というのを聞いたまあちゃんがとってもうれしそうに安心した顔をしたっていうのは、お母さんはぼくに指がなくてもぼくのこと、好きなんだ"って感じ取ったからではないでしょうか。まあちゃんは指がなくたっていいんだ〜お母さん、まあちゃんが大好きだもんねってことなんでしょうね。自分が親にきちっと受け止めてもらえている安心感。愛されているその安心感が子どもを成長させるんじゃないかなとわたしは思います。
幼稚園遊びで、さっちゃんは
これは父母の会の会員が実際に子どもたちにしてきた説明です。別にみんなで決めたわけでもなんでもなく、共通していましたね。生まれつきだということをみんなはっきりこどもに伝えています。父母の会設立当初の頃は扇風機に挟んで指を落としたとか、自動車のドアに挟まって指が切断されてしまったとか、「先天性ではなく、後天的な事故だというふうに子どもに話して聞かせる家族」もあったんです。でも3年生か4年生くらいになると、子ども自身が気付いていくんですね、ケガじゃなく生まれつきなんじゃないか、と。先天性っていう言葉にこだわっている家族は、親が先天性ということを隠し通そうとしている家では、手の話題をタブーにしているケースがよくあります。なるべく手のことに触れまいとしがちなんですね。そうすると、子どもはものすごく敏感ですから、手のことを親に聞くと親は悲しむ。親に聞いたってどうせわからない。聞いたって自分の指は生えるわけじゃない、と。そして手のことでの悩みや苦しみを家では語らず、一人で抱え込んでしまいます。このことの方がどんなにかかわいそうなことかと私は思います。
ある時、自分の障害は先天性だって気がついたり、近所の人の不用意な言葉から知った子どもは深く傷つくんですね。先天性に対する肯定感が周囲のどこにもないわけですから。だからわたしたちは、「生まれつきだっていいんだよ、うまれつきは恥ずかしいことでもなんでもない」ってことをはっきりと子どもにも社会にも伝えたい。『さっちゃんのまほうのて』のこのお母さんの言葉は目の見えない子ども、耳の聞こえない子ども、あるいは内臓などに先天的な疾病を持った子どもが、なんでぼくだけこうなの?って聞いてきた時の説明にもできると思うんです。先天異常っていうのは、だれにでも起こりうるアクシデントなんだって。人間の価値とは何の関係もない、そういうふうに世の中の人が受け止めてくださるとうれしいんですね。
でも子どもの心の傷はやっぱりかなり深いです。登園拒否というか、幼稚園に行けなくなってしまう。たばたせいいちさんのすごさ。絵本でこんなにシビアと言うかシリアスな絵ってないと思うんですね。本当に。このお風呂場の絵のページです。
さっちゃんが産院に赤ちゃんに初めて会いに行った場面です。お母さんもニコニコ、お父さんもうれしそう。
産院からの帰り道にお父さんと手をつないで歩きながら、お父さんに、"さっちゃん、お母さんになれるかな?"って聞くんですね。もちろん幼稚園でどんなことがあったのか父親は知っているでしょう。お父さんは、"なんだ、さちこはそんなこと心配してるのか。さちこはお母さんになれるよ、立派なお母さんになれるよ"って言い切ります。
この場面の父親の言葉でタイトルとなった「まほうのて」を表現していますが、実はわたしが最初のころ書いた原稿では別の意味合いで「まほうのて」の説明をしていました。
その時の原稿というのは、幼稚園でみんなで折り紙でつるを折っている。不器用な子もいれば、折り紙なんてやりたくない子もいる。ある一人の男の子がいいかげんに折ったでぶでぶのつる。さっちゃんは手首の関節とか肘の関節を使って上手に折り紙を折ります。父母の会の子どもたちは生まれつき指がないけれど、それなりに自分で工夫して上手に手足を使います。その子の手の使い方、足の使い方が本人にとっては正常なんですよ。さっちゃんもそうです。先生が、さっちゃんの折ったきれいな首も羽もぴんとしたつると、いいかげんに折られたつるをみんなの前で見せて、みんなどっちのつるが上手?って子どもたちに聞くと、さっちゃんのつるがきれい!って。そうよねー、さっちゃん上手ねーって言うと、子どもたちの中から、さっちゃんすごーい 手がないのにこんなに上手に折れるー、さっちゃんの手ってまほうのてみたいだねって子どもに言わせる場面を書いたことがあります。障害があっても努力して頑張れば、みんなとおなじようになんでもできるよ、だから"魔法の手"なのだという意味合いの原稿を書きました。
そうしたら編集会議で異論が出ました。しざわさんから、わたしも頑張れ頑張れって言われてきた、でも、障害者が歯をくいしばって頑張って初めて健常な人と同じレベルになることが、いいことで、それをほめてまほうのて、とするのはどうだろうか、と。たまたまこの絵本では、片手の指だけがない女の子をモデルにしてますけども、父母の会には両手のない子、両足のない子、両手両足のない子どもなど、重度の子がかなりいます。そういう子どもたちは、どんなに頑張っても普通の子とおなじようにできないことがいっぱいあります。そうすると、健常児と同じようにできることに価値をおき、「まほうのて」と賛美するような絵本でいいのだろうか、と。障害があることで友だちとは同じように出来ないことがいっぱいあっても、できないことはできないままでいいのだ、という視点がなければ子どもはシンドイ、というような話が出た記憶があります。頑張らなくてもいいんだ、出来ないことがあってもいいんだよ、周りの人がサポートするから、ってそういう社会にしないと、重度障害者の人は本当辛いです。健常児との比較は意味がない。だからこの絵本では、頑張るって言葉、一言も使っていません。頑張らなくてもいい、ありのままでいい、出来ないことがあったら出来なくてもいい。そういうふうに子どもをとらえる絵本にしようと。
その人といると、何か力をもらえる。そういうことって本当にあるんですよね。寝たきりの人を寝たきりで何にも出来ないから生きている価値がないとみる見方、それは違いますよね。その人がそこにいるだけで、そこに存在しているだけで家族のきずなが深まったり、家族に生きる意味を教えてくれたりすることがあります。障害を持つ我が子と生きることで逆に励まされ、人生のより深い意味に気づかされる、という障害児の親は多いのです。それをお父さんの言葉で最後の最後、表現することができました。ここはたばたさんが最後に手を加えた文章です。
たばたせいいちさんは、「このあきらくんは僕です、僕がモデルです」とおっしゃいましてね。この絵本の企画を偕成社から持ち込まれた時に、自分にできるかどうか自信がなかった、テキスト原稿を書く作業に自分も加わっていたけども、1年ぐらいはこの絵本を引き受ける決心がなかなかつかなかった、と。自分に障害児やその親の気持ちが、理解できるだろうかと。そこで、父母の会のスキーキャンプに来てくださったり、いろんな会に参加してくださったんですね。元気で明るくてかわいらしい子どもたちと接する中で、かわいい子どもたちを描く絵本、そういうかわいい子どもを育てている、いったんは絶望的な気持ちになったけどそこから生きる方向へ一歩踏み出してきた親たちを描く絵本だったら自分にも描けるかもしれない、と。父母の会と付き合う前は障害児とその家族へのイメージは重い人生を背負って頑張って生きている大変な人たち、というものだったそうです。ところが親しく付き合っていくうちに父母の会の親たちの、苦しみを引き受けてきた挙句の明るさ、やさしさに励まされているのは逆に自分の方だ、と。だんだん父母の会と付き合う中で障害児とその家族への見方が変わっていった、とも。
あきらくんは、自分の一言がさっちゃんを傷つけたって気がついたからこそ、さっちゃんまだ怒ってる?ってチョコレート持ってやってきたわけですよね。「さっちゃんがお母さんやるなら、おれお父さんやーめた」って、おままごとから下りている。さっちゃんのお母さんを自分は認めてない、そういうふうな自分に気がついて、さっちゃんの心を気遣って照れくさそうにやってきた。照れているあきらくんのひとことがさっちゃんの閉じたこころに届きます。いじめられて不登校になりがちな子どもがもしいたら、クラスに一人でも、その子の辛さ、さびしさ、苦しさをわかってくれる友だちが周りにいたら、その子は大丈夫ですね。その辛い気持わかってるよとか、自分は味方だよって、何かそういうメッセージを言葉にしてかけられるといいですね。あきらくんは照れくさそうにつぶやいて帰っちゃった、でもそういうことがあってさっちゃんは少しづつ元気になっていきます。お父さんに、お母さんになれるよ、さちこの手はとっても素敵な手なんだよって言われ、あきらくんが励ましにきた、幼稚園の先生がお星さまになってくれないかなあ、と声をかけてくる、そういった周りの人々との関わりの中でさっちゃんは幼稚園に行く力がでてくるのですね。
最後この、ジャングルジムの場面でお話は終わります。さっちゃんは再び幼稚園に行くようになり、お母さんになれないよって言ったお友達も一緒に仲良く遊んでる。たばたさんは、これは僕の夢です、この丸いジャングルジムは地球ですっておっしゃいました。現在はあんまりこの球形のジャングルジムは危険ということで児童公園にもないそうですが、これは地球で、地球を動かすのは子どもたち。子どもたちの中心に障害児がいる。障害を持つ子を中心に子どもたちのエネルギーや優しさがこの地球を動かしているんだ、動かしていくんだ、という夢というか願いを、この絵に託しましたって、講演会でおっしゃっていました。障害のある子もない子もみんな一緒に遊び、学び、支えながら生きていってほしい、そうした子どもたちのエネルギーでこの地球を動かしていってほしい、と。 時間が来ましたので、このへんで終わります。ありがとうございました。

(参加者):
わたしの子どもも心臓に欠陥がある子ですが、今は小学校に絵本を読むボランティアに行くようになり、『さっちゃんのまほうのて』を読ませていただいてます。この本に巡り合えてよかったです。
(野辺さん):
ありがとうございます。さっちゃんはお母さんから、お腹の中でけがをした、と聞いてもその時は納得できないんです。こんな手って言い方してますよね。こんな手って吐き捨てるような言い方から、まほうのてだもんって大きな声で言うようになる心のプロセスを描いた絵本でもあるのですが、さっちゃんがお母さんに「小学生になったら、さっちゃんの手、みんなみたいに生えてくる?」という場面があります。小学生になったら生えてくるか、ということは、障害は治るか?ということですね。子どもたちの夢かもしれません。こうした子どもと母親との会話は私たちの実体験です。
(参加者):
わたしは幼稚園児と看護学生を教えていますが、看護学生には『さっちゃんのまほうのて』を持っていって、患児の心理を教えています。
(野辺さん):
高校の保健体育の教科書にもね、ずいぶん差別的な記述がありました。特に遺伝問題など。今では優生保護法は撤廃されましたが、優生保護の見地から、結婚する時にはきちんと相手の家系や遺伝病の有無を調べた方がいいとか。そういうときにターゲットになるのが、外表奇形だったそうです。医学教育の場で先天異常への偏見について学生さんにきちんと話してほしいです。
(参加者):
わたしの息子も全く同じでして、お話を聞きながら追体験をしているようでした。写真のことも。自分は左利きだから、息子に右手をやりたいと。息子は小学校低学年ですが、いじめられることもなく過ごしています。今、習字を始めました右手を使って。父母の会のことは知りませんでしたが、お話伺えてよかったです。絵本の中では最後の父親の言葉がかっこいいなと思いました。
(野辺さん):
お元気にお過ごしのようで何よりですが、父母の会に参加されたらいかがでしょうか?仲間がいるのはいいことです。親は必要ないと思っても子どもさんは違うこともあるのですね。父母の会の中に子どもを連れてこないお母さんがいました。子どもに障害児ということを意識させたくないからと。でも、ある時お子さんが父母の会に行ってみたいと言って連れてこられた。そしたら、子どもさんは、今日はすごくほっとした、と喜んだそうです。きっと、毎日、健常者の中で、緊張しながら過ごしてきたのでしょうね。無防備な状態でいられる、仲間の中に入ることでほっとするのでしょうね、
孫にとっても、この絵本を読むことで自分の母親のことを理解できたようです。孫は毎年、クラスが新しくなると、「わたしのお母さんは右手の指がありません。今度家に遊びに来たら見てください。」と自己紹介してしまうそうです。隠すのではなくお互いに知り合って理解することが大切ですね。
(参加者):
お話を伺っていて、金子みすずの詩とまどみちおのぞうさんを思いうかべました。みんなちがってみんないい、おかあさんのはなも長いし、ぼくのはなも長い、おかあさんと同じでうれしい。
(野辺さん):
わたしにとって「遺伝ではありません」と専門医からはっきりと言われたことがずっと支えになっていた時期がありました。やはり、遺伝は怖い、という偏見と恐れがあった。でも、仲間が増えるにつれて遺伝性の人も増えてきた。親に子供が似て当たり前。障害があったっていいじゃないか、遺伝だっていいじゃないか、と今は考えています。父母の会では95年宣言の中で、障害があったっていいじゃないか、という、宣言を出しています。遺伝だっていいじゃないかという宣言を出そうという動きがあります。『ぞうさん』の歌を改めて思ったことがあります。
あるご家族は、おとうさんが指が3本しかなくて、生まれたこどもさんがふたりとも3本しかない。お父さんに似た子どもなんですね。その家族の中では、5本の指を持っているのはおかあさんだけ。おかあさんだけがその家族の中で異質なんです。でも幸せな家族です。本当に"みんなちがって、みんないい"ですね。
それでは、みんなで『ぞうさん』を合唱して終わりにしましょう。
■ 本の紹介 (終わり)
(終わり)
|
お問い合わせ: NPO「大人の学校」 住 所: さいたま市南区別所5-1-11 TEL/FAX: 048-866-9466 Eメール: otonano-gakkou@cure.ocn.ne.jp |
[制作] NPO(特定非営利活動法人) 大人の学校